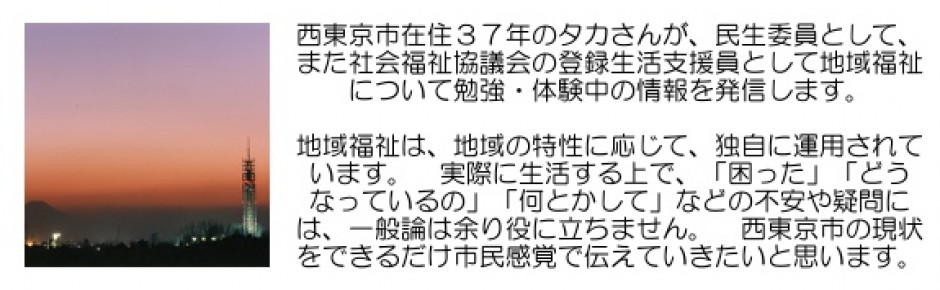新任民生委員研修3日目。以下、講義の概略を記す。
1.高齢者のための社会福祉 講師:和洋女子大学 岸田教授
話題の「消えた高齢者」問題で、民生委員の存在を持ち上げて本題へ。
まずは、高齢者とは?から。 法律では定義されていないが運用では65歳。 1950年代にWHOが65歳以上と決めたが、その時の日本の平均寿命は60歳以下。オランダでも75歳。65歳は現在では若過ぎ。個人差が大きく暦年齢は老化の指標とはなり難い。
高齢社会は悪い面が強調されているが、日本が世界に誇れる優れた特徴。環境や医療が優れている証拠。デンマークでは、医療の無償化が言われているが病気になるとまず予約。一週間も待たされるので、風邪など自然に治ってしまう。薬の消費量?は少なく済むが、これが成功か? 日本は幸せ。 また日本の65歳以上の就労率は世界一。 元気で長生きの日本バンザイ!というところ。 介護保険の先進国の西独は、現金支給で失敗している。一方、日本は現物支給で大成功。世界に誇れるシステムだ、とのこと。 本当ですか? 目から鱗だ。
高齢化の裏側は少子化。合計特殊出生率が1.29。 2.03で現状維持だから、いかにも少なすぎる。何とかしなければ・・・。
加齢による身体変化、精神心理面での変化は確かにあるので、認知症の高齢者は増大中。その67%は在宅、22%が大規模施設に入所。しかし認知症高齢者は集団生活が難しいことが多い。グループホームによる小人数介護が妥当か。 実際に増えているようだ。
高齢者を取り巻く法と施策では、高齢者の医療保険制度が試行錯誤中。引退した高齢者が市町村の国民健康保険に集中、偏在するので、保険が保険としての運用が困難になっている。後期高齢者保険は色々批判もあり、改革を迫られているが、構造的にはほぼ同じ仕組みにならざるを得ない。
保険は病気へのリスクだが、長生きのリスクに対応するのが年金制度。これも試行錯誤中。
介護保険制度改革には、予防重視型システムへの転換がある。最近は、要支援から要介護1の人が激増(介護提供事業者の誘導もあるようだ)しており、財政的な負担になっている。 これを抑えるために、介護予防事業が始まった。本来、予防は、保険には馴染まないが、背に腹は代えられない。(注:保険とは、なったら救済するもの)
また、施設に入所すると保険給付額が急増するので、在宅介護の支援も充実中。
財政難の話ばかりで、患者本人が置き去りにされている感もあるが、少ないお金を如何に構成に構成に分配するかが重要。 地域として関係機関、関係者が連携した支援を行う余地は大きい。 民生委員もその重要な一環と期待されている。
2.先輩委員の体験事例発表(高齢分野)
内容的には、社協の登録生活支援員の仕事と重複しており違和感はない。違いは、登録生活支援員は、社協に持ち込まれた後からの仕事だが、民生委員は、その潜在的なニーズの掘り起こしから始まること。地域社会への浸透をはかるための挨拶(とにかく挨拶)や老人会活動や地域行事への積極的参加など、積極的な努力を継続。ラジオ体操、おしゃべり会、誕生会などあらゆる機会を捕えている。 とても真似ができないと言う印象だが・・・・。
3.子どものための社会福祉 講師:前立正大学 片岡教授
少子化時代の現状からスタート。平均所帯人員は2.53人。児童のいる所帯の平均児童数は1.74人。その結果が密室の悲劇。母親の子育ての不安・不満と負担感。 これが、児童虐待の背景。 少年非行にも関連。その他、DVと子ども、ひとり親家庭と子ども、障害をもつ子どもの支援などが説明された。 重い問題だ。 解決策の一つが、地域に子育て支援のしくみをつくる事。民生委員もその一員。
児童健全育成と児童福祉文化など、立派なことが一杯書いてあるが、実際は?で話は終わった。
4.先輩委員の体験事例発表(子どもの分野)
児童虐待であるネグレクトのケース。小学校校長からの連絡で、児童館と連携して支援。高齢者の場合と同様に、民生委員に相談が来るような普段からのネットワーク作りが重要。短期間に信頼関係は構築できない、というのが実感。学校の校長も児童館の館長も数年で交替するのも課題だと感じた。
5.座談会「あせらず、ゆっくりはじめましょう! 民生委員・児童委員」
地区民児委員協議会会長2名が先輩委員として参加。数人のグループで①民児委員活動の中で感じたこと、②疑問に思ったこと、③先輩委員に聞いて見たいこと、を討議。 とは言え、7月に民児委員になったばかりなので、「まず何をして良いかが分からない」というのが最大の感想であり疑問であり、質問したいこと。 個人的には、「あせらず、ゆっくりはじめましょう!」の掛け声は、待ちの姿勢を進めているようで、少々、頼りなさを感じた。
今回の新任民生・児童委員の集合教育で驚いたのは、各地域での民生委員の活動がバラバラなこと。地域の中でも、全く違っているとの協議会会長の発言もあった。 民生委員の活動状況もその委員のやる気によりバラバラなようだ。
大丈夫、その内、忙しくなりますから、の説明は本当なのであろうか? 杞憂なら良いが。
一応、これで新任研修は終了。過去に受講した社会貢献型後見人の養成基礎講座や社会福祉協議会の登録生活支援員の導入教育と実習などと重複する部分が多く、復習しながら新しい発見もあり有意義であった。