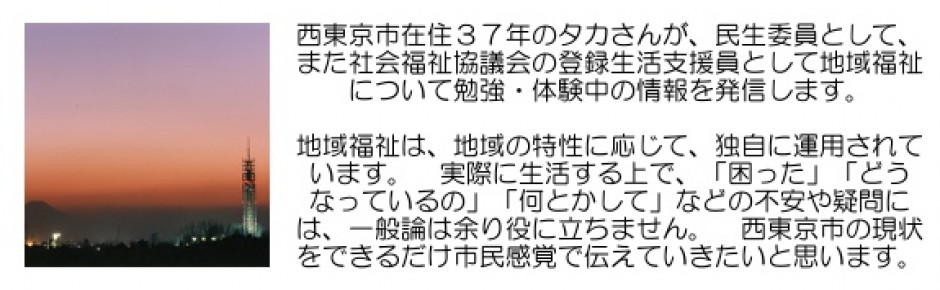テーマは「民生委員の役割と活動状況について知る」。富士町地域包括支援センターの主催。参加者は、ささえあい協力員・訪問協力員と協力団体。私は、ささえあい訪問協力員(昨年7月に登録)として出席案内があり、名札もそうなっていたが、急遽、民生委員として前方の席に座らされた。 7月に民生委員になったばかりなので、地域包括支援センターがうっかり?していたようだ。
民生委員側から生々しい活動状況が説明され、質疑も盛んであった。懸念は、地域福祉に関心がある出席者が、民生委員の役割や地区の民生委員の名前や顔をしらなかったこと。民生委員の個人名や電話番号については、年1回5月の市報に掲載されるだけ。 皆さんが知らないのが当然。 となると、新米民生委員としては、地域住民の前に顔を曝して、名前を覚えてもらうしかない。
どうやら、地域には既に多くの高齢者に関わるグループがあるようだ。これらの活動に地道に参加するのが一番効率的なようだ。 しかし、老人会は老人になったようで苦手だな・・・。 組織率も低下一方のようだし。 私が参加している太極拳教室は老人会の雰囲気もあるが、一応、若い人もいるので抵抗はない。 75歳位までは老人の自覚がない人が多いのではないか。 老人会という名称を変えた方が良いかもしれない。
社会福祉協議会から、ふれまち(ふれあいのまちづくり)への参加を打診されている。ココから始めるのが適当か。 しかし、「ふれまち」も知らない人が多い。後継者が少なく、平均年齢は上がるばかり。 とは言え、町内会も自治会もないので、「ふれまち」と、最近話題(?)の「ほっとネット」(これも知名度は低いが)を盛りあげるしかない。 先輩の民生委員が、先行きに弱気なのが気になるが・・・。