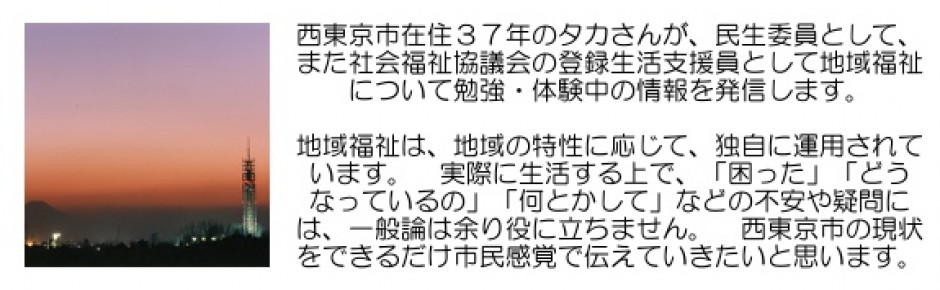新任民生委員研修2日目。1カ月ぶりに同期に再開。社会福祉協議会の導入教育などと重複・補完するので理解しやすい。以下、講義の概略を記す。
1.民生児童委員の実際
東京都の民生児童委員1万名から毎月提出される活動記録から見える活動の紹介。
まずは平均年齢:民生児童委員は61.9歳。男女比は、73.2%が女性。 西東京市は女性比率が約9割と高い。これは、西東京市がベットタウンなので、平日、時間的に余裕のある男性が少ないせいかと思われる。
活動日数は、12.1日。毎月1/3は何らかの活動がある。が、相談・支援件数は2.1件と少ない。一方、訪問回数は13.6件。行政からの依頼仕事が多いようだ。
対象者は、63%が高齢者、子どもが15%、障がい者は7%。 地域毎に活動内容異なるので、平均値による単純比較はできないようだが、参考になった。
2.地域福祉の支えてとしての民生児童委員 講師:淑徳短期大学 塩野教授
「社会福祉における地域福祉の位置付け」から講義を開始。 1947年施行の日本国憲法と2000年施行の社会福祉法から、社会福祉の定義や目的、基本的理念、地域福祉の推進主体を解説。国が実現すべきことを、抽象的だが明確に規定している。
問題は、地域福祉を誰が具体的に推進するのかだ。 行政が全てをしてくれるわけではない。まずは「自助」。 次が「互助」、「共助」、「公助」。 「共助」は、他人の幸福を願って、自発的に自分の時間、労力、金品などを提供するもの。民生委員は、正にこの「共助」に属する。
民生委員の役割は色々あるが、まずは「住民ニーズの発見」。次に「つなぐ」、「エンパワ」、「バリアフリー」だそうだ。 住民の福祉ニーズの説明では、「マズローの欲求5段階説」まで飛び出した。
最後は、地域福祉の構成要素の解説。ここで赤十字の<人道の4つの敵>の紹介があった。「利己心」、「無関心」、「認識不足」、「想像力の欠如」の4つ。「自分さえよければ…」、「そんなことに興味はない…」、「知らなかったから…」、「そんなことになるとは思わなかった…」、という心の弱さが敵ということ。
抽象的な話で、現実との乖離も感じたが、社会福祉や地域福祉について大局的な観点から整理され、非常に勉強になった。
3.低所得者のための社会福祉 講師:埼玉県立大学 長友准教授
最後は、生活保護の仕組み解説だが、それまでの説明が面白かった。生活保護の仕組みは、西東京市市役所の担当部門から説明を受けたばかりであったが、現場から大学教授に転身した実務家の話は、目から鱗の内容が多く、もう一度勉強し直したい内容であった。
4.障がい者のための社会福祉 前立教大学 赤塚教授
障がいには、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害などがある。各々については、既に社会貢献型後見人養成講座や社会福祉協議会の導入教育で聞いた話が多かった。
障がい者の表記は、本来は障碍者、法律的には障害者、最近は障がい者というところまでは認識していたが、新聞雑誌では、障害をもつ人、障害がある人と言い換えているとは知らなかった。
障害者自立支援法が廃止され、新たに総合福祉法(案)が平成25年8月に制定される予定。その理由の説明があった。が若干歯切れが悪い。 もう逆戻りすることはないが、今後の進展を各自関心を持ってフォローするようにとの説明が最後にあった。 まだまだ不透明な部分が多いようだ。