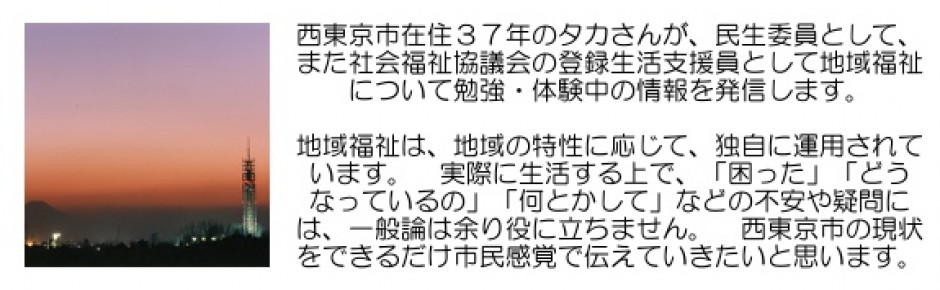地方財政分析の講義で、歳入の勉強をした。 その際、日本政府の借金は900兆円超、地方自治体の借金は200兆超、計1100兆円の借金は、ギリシャを超えた、日本の財政も危ない、というように書いた。 先生がそう解説したし、新聞やテレビでもそう報道している。
しかし、日経ビジネスによると、ギリシャの借金と日本の借金は全く別物なので、単純にその絶対額を比較するのは愚だそうだ。
政府の借金は、① 政府が自国通貨建てで自国から借りた負債、②政府が自国通貨建てで他国から借りた負債、③政府が外貨建てで他国から借りた負債、④政府が共通通貨建てで他国から借りた負債で、ギリシャ政府の負債の7割は④ に当たり、日本政府発行の国債の95%が① である。さらに日本政府の場合、外国人が保有する国債についても ② に該当する。すなわち日本の場合、過去に発行した国債の、ほぼ100%が日本円建てなのである。
ちなみに、アメリカ政府の負債は①と②が半分ずつで、2001年に破綻したアルゼンチン政府の負債の多くは ③ であった。
債権者が国内投資家だろうが、あるいは海外投資家だろうが、国債が自国通貨建てである限り、現在のギリシャが陥っているような「政府のデフォルト(債務 不履行)」の危機は生じ得ない。政府の資金調達、すなわち国債発行時の金利水準が上がっていけば、中央政府が国債を買い取る(=買いオペレーション)こと で、金利を抑制すれば済むだけの話なのだ。
ということで、それ程、大騒ぎしなくても良いらしい。 上記記事では更に国債を増発しろと主張している。 しかし、借金は怖い。 やはり、このまま国債増発をするのは限界のような気がする。 ロジカルではないかもしれないが・・・。