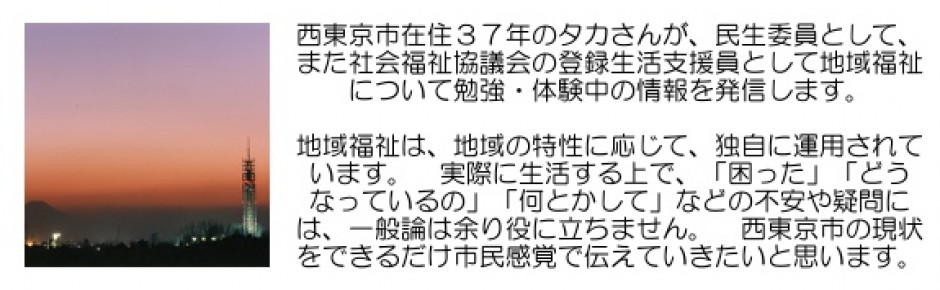本日は、地域包括支援センター(以降、包括と略)からの緊急要請で、郵貯銀行での払い出しを行う相談員に同行。前回は某都市銀行での定期預金の解約と預金の払い出しを経験。今回は預金通帳を紛失し、キャッシュカードは暗証番号を忘れたため、現金が引き出せないと言うAさんの支援。
Aさんは歩行困難で、判断力も衰えている。自分では郵貯銀行に行けないし、金銭管理も困難。 どういう訳か、ありとあらゆる支払いが滞って、電話は既に停止、家賃3ヶ月分滞納で明け渡しを要求されているとのこと。現金は、家に数十円しか残っておらず、このままでは餓死、という緊急事態だそうだ。
そこで、まずは、Aさん宅近所の郵便局で、通帳再発行と暗証番号調査の申請書を入手後、Aさん宅に出向き、待ち構える包括スタッフとケアマネと合流して、必要な項目を本人の自署してもらって、再度、郵貯銀行に書類を提出する、という予定を立てた。 さて、実際は?
事前に、郵便局に電話で事情を説明してあったので、通帳の再発行、暗証番号の調査、及び印鑑の改印に関する白紙の委任状と記入方法まで順調に終わった。次に手続きの確認中に、重大な問題が生じた。
郵便局に委任状を提出した際に、郵便局から本人に電話を掛けて、委任状の内容が本人の意思かどうかを確かめる、というのだ。 念には念を入れるということ。 しかし、本人自宅の電話は、料金未納で止められた状態。 電話での確認は不可能。 郵便局も便法はないかを調べてくれたが、例外は認められないと言う結論。 自宅へ訪問してくれるサービスもあるが、それでは、間に合わない。 できるだけ早く、現金が必要なのだ。
色々、電話でのやり取りが続いて、結局は、Aさんを車に乗せて、郵便局に来て貰うことにした。 最近は寝たきりなので大丈夫?というところだが、餓死するよりマシ。
次の課題。通帳の再発行や暗証番号は、1週間程度で書留で郵送されることが分かった。 が、本人は寝たきりで受けとることができない。 ならば、不在通知書が残されるので、代理人が委任状をもって、本局まで取りに行くしかない。 誰が郵便受けをチェックするのか? 委任状の書き方は? 等々、抜けがないように何度も頭の中で予行演習。
Aさん到着。包括スタッフとケアマネから詳細状況を確認。 滞納の原因が分かった。 新たに通帳を作って、年金の振込み先口座を変更したので、旧口座の残高が空になったせい。 なぜ新口座を開設したのか理由は不明だが、年金が新口座に入っている可能性が高い。 少なくとも今月15日には、2か月分の年金が振り込まれるので、それまでの辛抱。 だが、辛抱できないものは何? 東電からの催促状を確認すると、つい数時間前に電気が止められたことが分かった。 電気が止められたら、エアコンが効かない。 冷蔵庫も動かない。 酷暑の中で、とても生きていけない。 一刻の猶予もできない。 東電に電話すると、一か月分でも支払えば、通電を再開するそうだ。 4000円を何とかせねば!
早速、通帳再発行と暗証番号調査の手続き開始。申請書は、本人の自署でなければダメだそうだ。 前回の都市銀行でも、同じことを言われたが、何とか切り抜けた。 今回も、色々工夫して、とりあえず申請は終了。 後は通帳と暗証番号が郵送されるのを待つだけ。 その間の一週間はどうする?? まずは、東電滞納分の4000円だ。 誰かが立替えるか? 餓死するのを座視はできない。 セーフティーネットはないのか? あった! 生活つなぎ資金融資の一つである一時援護資金。 所得制限なし、保証人不要で2万円を融資。 一週間後には、年金が入っている通帳が届くので、焦げ付きの心配はない見込み。 早速、市役所の生活福祉課に相談して、融資の了解を得る。 電気代滞納分4000円を支払っても残りは16000円ある、との見通しがたったところで、今後の本人のケアをどうするか、簡単に打ち合わせ。
どう考えても、在宅の独居は難しそう。しかし、施設に入れるにしても、本人の健康状態が不明。 一週間前まで一応歩けていたのに、何故急に容態が悪化したのか? ということで、郵貯銀行から、包括スタッフとケアマネが本人を病院へ、我々は市役所の生活福祉課へ直行。とりあえず、東電へ一か月分の電気代を入金。 帰宅は問題なくできることになった。
この、生活援護資金は、容易に借りることができるので、不良債権化しやすいそうだ。 小額とはいえ、ちりも積もれば山。 税金の無駄遣いは許されない。 特に本人が出頭できないので、(代理人が社協とは言え)厳格な委任状が求められた。 もし過去にこの一時援護資金の返還を怠っていると、このセーフティネットも使えないそうだ。 今回は、初めての申請だったので、本当にセーフティーネットとして機能した。 もしダメだったら、後数時間、知恵を絞ることになったろう、と思うとゾッとする。
今回のケースでは、急激に様態が悪化した本人を囲んで、包括、ケアマネ、社協が必死になって、援護の方法を探した。 悠長に会議を開いて慎重に検討など不可能。 目の前に溺れている人を、どう救うか一刻の猶予もできない状況。 情報も不確かで想像、類推、推理の連続。 家に残された各種の領収書や請求書、手紙などの断片的な情報から、パズルを解くように、滞納の原因から年金の在り処を探った。 鳩首会議の場所が、郵貯銀行の窓口だったこともあり、郵貯銀行のスタッフからも全面的な協力を得た。
福祉の現場は実践力が求められる。 社協の権利擁護事業としては、契約してからと言うのが原則だが、その原則に拘っていると、溺死者の山になる恐れがある。 介護保険の導入で、福祉サービスは「措置から契約」へと移行したが、契約前の対応を柔軟に応急的な措置として行わないと、制度として機能しないことが実感できた。
机上では学べない貴重な半日の経験でした。 それにしてもAさんは、危なかったなぁ・・・。