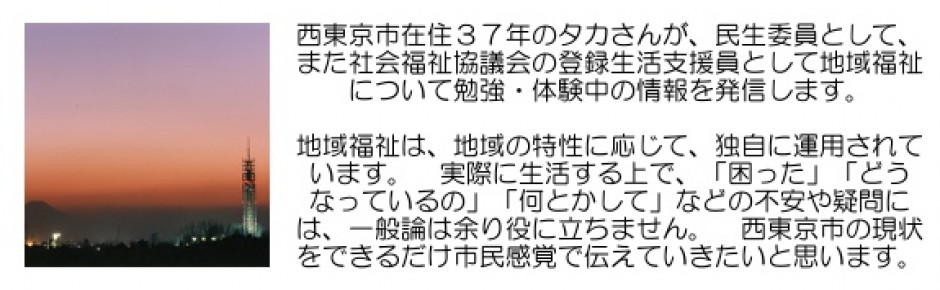社協の日常生活自立支援(権利擁護)事業から成年後見にスムースに移行するには、市民後見人の養成が大切だ、という論文を読む。 要旨は以下。
社協の日常生活自立支援事業は、平成12年の介護保険施行に先立って、要介護認定判定の開始時期に併せて施行された。 社会福祉が措置から契約へ移行するのに伴い、判断能力に不安がある人に対して、福祉サービス利用契約支援や日常的な金銭管理を、行政や地域包括支援センターと連携して支援するのが役割。 この判断能力が更に欠ける常態になると、成年後見制度により、利用者の判断能力のレベルに応じた支援が行われる。 当然、日常生活自立支援事業から成年後見への移行に際しては、切れ目のない支援が要請される。
しかし、社協の担当する日常生活自立支援事業は、低所得者層を対象としており、成年後見についても、適切な後見人等の候補者がいない場合で、その大半が、生活保護受給世帯や住民税非課税世帯という低所得者に限られている。
となると、公費助成を行ったとしても、専門職による成年後見人を依頼するには、金銭的に難しい場合が多いと予想される。
ここで登場するのが、地域福祉と市民参画である。 即ち、地域の課題を地域で解決するという地域福祉の基本的な考え方に立脚し、その担い手として市民後見人を位置づけることによって、更に重層的な地域福祉の推進に寄与せしめる。 自助、公助の中間に共助、または互助を考えようと言うもの。 「新たな公共」である。 参画型社会福祉である。 この仕組みを機能させるには、市民後見人の定義の明確化や養成と活動支援のシステム構築、地域力の活性化等が必須だそうだ。
要するに、それなりにお金のある人や恵まれた家族環境にある人は、専門職後見人を依頼することは可能だが、低所得者層や独居高齢者などは、地域社会が支えなければならない、ということのようだ。
上記の観点からは、西東京市はかなり真面目に市民後見人の養成に取り組んでいるように見える。 登録生活支援員として実習中の我々6名は、今後の西東京市の市民参加型社会福祉のモルモットのようなもの。 かなり責任が重い、と感じた。