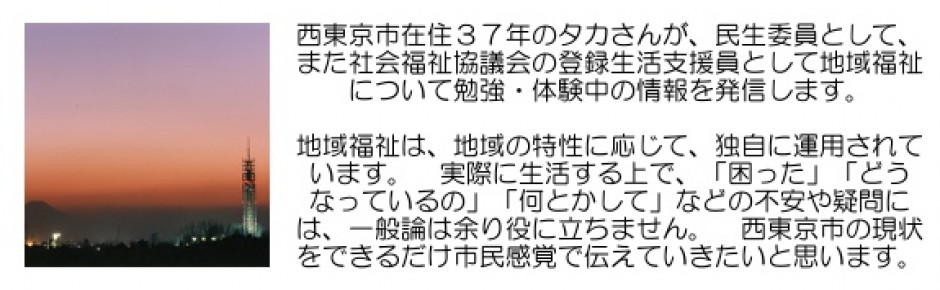月に2度の自宅訪問。 今回で2回目。 前回同様、先任生活支援員と担当相談員に同行。
あなた方は誰? 何の御用? 認知症とは聞いてはいたが、やはりちょっと驚く。 でも元気なものだ。 気配りも忘れない。 直にクーラーを入れてくれた。 何回か通ううちに、名前は無理でも顔は思い出してくれるだろう。 次回からは自分で作業できるように、先任支援員の手順を必死に覚える。 掛け時計の電池が切れていた。 電池の購入は生活支援員の仕事ではない。 ヘルパーなどに頼むことになるだろ。 都の新任生活支援員の集合研修では、電球の交換をしてはいけないと教わった。 何か杓子定規な感じもするが、本来やるべきところが(なければそれを手配して)やらないと、仕組みとして長続きしない、ということらしい。 ちょっと考えさせられた。
事務所に戻って、報告書をパソコンで作成。 前任者の報告書を真似て何とか完成。 今月の2回の訪問で、利用者の様子の基準を自分なりに掴んだので、今後はその後の変化を注意深く観察・記載していくことになる。 自分の感情を交えず、事実を淡々と記載するのがコツ、だそうだ。
それにしても、炎天下、自転車で利用者宅を訪問するのは辛い。 普通は、利用者は節約の為にクーラーをつけないことが多いので、夏場の自宅訪問は炎熱地獄のようだとか・・・。 冬はどうなるのだろう・・・。 暴風の日は・・・。 甘い! 渇!
2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
最近の投稿
カテゴリー