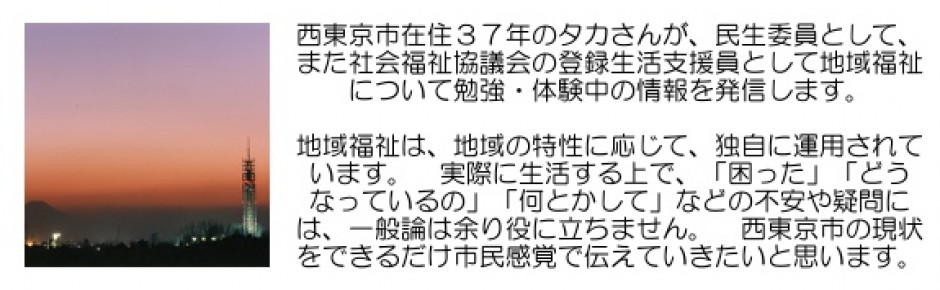地域権利擁護センター「あんしん西東京」での実習(7月から毎週水曜日、8時半から17時までの終日勤務)、その2日目。
8時半からグループ内ミーティングに参加。各人からの当日の予定と昨日の業務報告。前回より皆の話についていけるようになった。それにしても個人情報の氾濫。 グループ内で情報を密に共有する理由は、本グループが対応している人々が、判断能力などが不十分で、状況が曖昧で流動的なこと。 決まりきった対応方法がなく試行錯誤せざるを得ないこと。個人での対応でなく集団知・経験知で解決していく必要がある。
今朝の議論を抽象的に述べると以下
1)ケアマネージャやヘルパーへの苦情や交代要求があったとしても、一時的な感情的発言や被害妄想的な発言かもしれない。 介護保険適用前後では、よくある話で、その後の対応や冷静になって考えたら、印象が全く変わった、ということも多い。
2)生活保護に関する誤解も根強い。 利用者のプライドの問題もあり、思い込みの強さは尋常ではない。そう信じ込ませておいても特に支障がない場合は、そのまま放置するのが賢明。
3)異常にケチケチの人がいる。洗濯機の乾燥機能が壊れたので、ヘルパーさんが手で絞っている。体力的に辛いし、時間ももったいない。洗濯機を壊したと騒ぎ出すかもしれない。生活保護を受けているので、そこまで切り詰める必要はないが、聞く耳を持たぬ。どこから中古品を入手するのが一番。
4)高齢者に対する虐待も、本当に虐待かどうかの判断が難しい。 通常、虐待するのは親族なので、解決方法にも気を使う。 親族内の騒動にも発展しかねない。 社協の介入の仕方が難しい。
5)4人部屋から個人部屋への転居希望があった。被害妄想的な不満が原因だが、本人は一応満足したようだ。しかし、暫くすると気が変わるかもしれない。 気が変わらないうちに、手続きは進めたほうがよい。
6) 利用者の中に、自分で通帳を管理したいと希望している人がいる。どうも親族が何か言ったらしい。しかし、実際には無理。本人もそれを分かっている。だが、フラフラしている。・・・・
7)後見人が必要。親族を探したが、息子と弟も海外。 どう連絡をとったらよいか・・・。
8)後見人が必要だ。誰が申立てるか? 後見人をだれにするか?
9時半からグループ内会議では、もう少し中長期的な管理体制について議論された。 最も白熱したテーマが、「成年後見申立支援事業の業務範囲について」。
「あんしん西東京」として、日常生活自立支援事業は明確だが、対象者の判断力のレベルは千差万別。置かれた状況により、また健康状態により変化・変動する。 「判断力に欠ける」と言うのは簡単だが、実際の判定は容易ではない。 あるレベル以上は、日常生活自立支援事業で、あるレベル以下は、成人後見人制度で、などと明確には線引きできない。
一応、判断能力のある人は、日常生活自立支援事業の対象だが、ない人はどうするか? 「本人」は、判断力に欠けているので、自分では判断できない。 周りの人が、本人の意思を推測して、後見人の申立をすることになるのだが、本人の意思は? 誰も分からない。 ひょっとしたら無理強いしているのでないか。 一時的に判断力が戻った時の判断を尊重しても良いのか、悪いのか? などなど、悩みは尽きない。
また、社協は市長申立の場合は、主体的に申立の支援を行うが、それ以外の申し立て、例えが家族や親族、また専門職後見人の場合に、成年後見申立支援を事業として行って良いかも問題。 所謂民業圧迫にならないか!である。 社協は、実質的に行政の一部なので、その立場で事業を行うと、その領域を事業とする民間業者が困る事にならないかという懸念。
しかし、後見人制度の適用を考慮してから実際に申立を行うまでには、数年を要することも多い。この間、民間業者が本当に親身になって対応してくれるかが心配。
また、収入の少ない(資産はある可能性があるが)高齢者は、金銭的な心配から、専門職後見人への依頼を躊躇する例もある。そのまま放置しておいてよいのか。などなど。色々考慮すべきことが多い。 (この業務範囲の部分は、私が勝手に補足した部分が多い。社協の見解ではない。文責原)
10時過ぎに高齢者専用住宅(シルバーピア)である市営住宅オーシャンハウスに相談員と出かける。 入居者が市役所に提出する書類作成のお手伝いが目的。 色々興味深い話を聞くことができた。 別途、投稿する。
午後14~16時の西東京市精神保健福祉連絡会に参加するため、多摩小平保健所に相談員と出かける。西東京市の精神障害者を支援する関連団体が毎月一度集まって交流・勉強する集まり。 Aさんを事例に、各団体がどのような援助ができるかを話し合い、マニュアル化することを目的としている。若い人が大勢参加しており、またまた勉強になった。 これも別途投稿したい。
16時半に事務所に戻る。 相変わらず相談電話が多い。 「何、生保が打ち切られた? そんな馬鹿な! 何かの間違いではないか・・・・」等々の言葉や叫びが飛び交う。 利用者に味方、「あんにん西東京」を実感する。
ところで、福祉の世界では、略語が飛び交う。 シャキョウは、社協で、社会福祉協議会の略語。これには慣れた。 上記の「セイホ」は、生命保険? 残念! 生活保護の略語。 何度聞いても、反射的に生命保険が頭に浮かぶ。 生活保護が出て来れば、一人前か。 「ホウカン」は? 幇間? 答えは訪看。 訪問看護士の略語。 「ホウカツ」は? ソウカツの聞き間違い? 答えは包括。 地域包括支援センターの略語。 チケンは、地権。地域権利擁護事業の略。 まだまだありそう。 慣れるのが良いのか? 少々疑問だが、慣れるしかない。