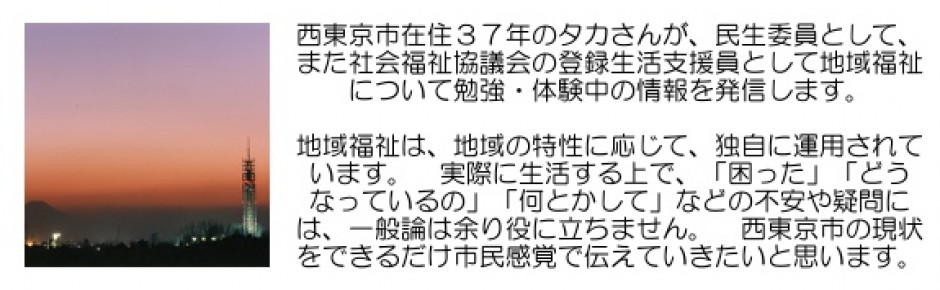講師:鈴木 健司さん あんしん西東京運営審査委員会委員 弁護士
実戦でバリバリ活躍中の弁護士さん。 少し小太りで威勢が良い。 にこやか、ざっくばらん。還暦前。
イメージが湧きますか? 無理ですね。
最初に、六法全書をドンと開いて、相手がタジタジするのを面白がる、風に見えた。
法的制度の説明なので六法全書が出てくるのは当然かもしれないが・・・。
後見・相続・扶養に関する法的制度については、今年1月の「社会貢献型後見人等候補者の養成基礎講座」で、数時間に亘って二人の弁護士から説明を受けた。 今回の講義は、そのほんの一部。 だが、時間が短いだけに、実務上は何が本当に大事かを、簡潔に指摘。少人数、Q&A形式で、分かりやすく楽しい講座だった。(重箱の隅を突くようなQには、ちょっと曖昧なAもあったが)
後見人とは? 福祉が措置から契約に移行。 対等な契約をするために、判断力に欠ける人を支援。 具体的には身上看護と財産管理(保全)。 で、何を知っておけば良いの?
まず、親族の話。 なぜ親族の話か? 後見申立てができるのは親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のみだから。また、扶養義務や相続権についても、親族の範囲の知識は、必須。
次に、扶養義務の話。 後見人としては扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の(扶養の意思の)有無の確認が必要。 扶養は介護と密接な関係があるため。 (タカさんとしては、戦後に「扶養義務と相続権を切り離して処理」することになったことが、後見人が必要になった一因と思う。 要するに、家が崩壊して、核家族化した事を言いたいのですが、・・・)
次に相続の話。 後見人としては、相続を貰う方が大事。 要するに相続人の権利を行使することが重要。
油断すると、無視されることがある。 何しろ被後見人は、判断力がないので。
権利を侵害され、そのまま放置しておいたら、後見人の責任。場合によっては弁済をしなければならない。
注意するのは遺留分減殺請求。と、被相続人の債務超過の疑いのある場合は、限定承認か相続放棄の申請。
遺留分減殺請求は、単独で一方的にできるが、限定承認は相続人全員で、また相続放棄も実質的には全員でする必要があるので注意!
最後は、後見人の仕事。 財産管理では、最初の財産目録の作成が超重要で、且つ超苦労。これ自体は、色々噂を聞いているが、やはり事実だそうだ。 その他色々なノウハウの話があり、参考になった。
身上看護については、社協の地域福祉ネットワークの活用が大事なことを再確認。が、過信はできない感じもあった。色々なネットワークがあるようなので、自分で調べることも大切。 何しろ後見人なのだから、最善は尽くさないと。
最後に、被後見人の遺言の制限の話あり。 要するに、第三者である後見人は、被後見人から遺言で財産を貰っては駄目ということ。 倫理上、当然だが、医者などでは、時々聞く話です。
後見人は、オールマイティなので、悪いことをしようと思えばできる立場。後見監督人がついても、なかなか見破れないとの話を聞いたことがある。 弁護士や司法書士、社会福祉士など職業的後見人(倫理規定が徹底している)でも、誘惑に負けた人が沢山いるそうだ。(時々ニュースで見かけるが、氷山の一角の可能性もあるのかな?)
市民後見人が担当するような人(市長申立)には、財産のある人は少ない?から、その恐れはない、というのが社協の説明。目の前に誘惑?がないので安心ですね。 自戒!自戒!
(5月25日受講)