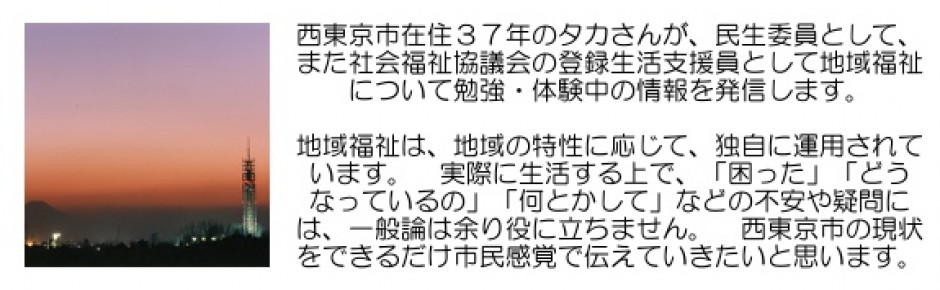15回の机上研修と2回の実習を終了。いよいよ7月から実際のケース(利用者対応)が始まる。
4月からの3ヶ月の研修を振り返って見ると、「登録生活支援員」に対する西東京市及び社協の手厚い養成計画が感じられる。
最初は「登録生活支援員」とは、何かも分からなかった。 社協としても初めての経験で、試行錯誤があったそうだ。
元々、東京都が進める「社会貢献型成年後見人等候補者の養成基礎講座」の終了者に対する実習として、西東京市社協として独自に設けたもの。 東京都社協が実施した新任生活支援員の研修では、他区市では西東京都市のような研修を行っている例は少ないようだ(登録生活支援員の制度自体もないようだが)。 西東京市社協でも、従来型の生活支援員には、今回のような手厚い研修はしてこなかったとのこと。 幅広く総合的に地域福祉に関する勉強ができて、非常に幸運であったと感謝している。
尤も、登録生活支援員6名の内、3名は上記養成基礎講座の終了者だが、3名は今年度の受講を予定している。 予定としたのは、西東京市では「社会貢献型成年後見人等候補者の養成基礎講座」の受講希望者を、市内から公募するのが原則だから(8月1日の広報で告知予定)。 幅広く市内の受講希望者に門戸を広げるのが趣旨。 昨年度は(昨年度から公募が始まった)、8名の希望者から2名が選考された。 後見人等候補者の資質があるか否かは、総合的に判断されるので、登録生活支援員だからといって、絶対に選考されるとは限らない。 後見人等候補者を目指して基礎講座受講希望者の我が同僚3名は、かなり不安・緊張の様子。
7月から実際の利用者を担当、とは言っても、実際に1人で対応する訳でなく、7、8月は、現在担当している支援員と相談員に同行して、支援方法を学んだり、利用者との関係作りをする、移行準備期間。 9月以降に支援員としての業務を引継ぐが、当面は相談員が同行して指導をしてくれるそうだ。 本当の1人立ちは、それ以降。 (何しろ地域福祉の現場を知らないのだから)研修の延長のような状態がもう少し続くので少々安心。
新任支援員が担当する利用者の具体的な説明があった。 個人情報保護の関係で詳細説明はできないが、いずれも新任支援員が担当しても問題がないようなケース。 月1、2回自宅を訪問して、利用者の日常生活の自立支援を行うことになる。
利用者の自宅訪問による生活支援は、事前事後処理も含めて半日ほどの負荷。 その実働時間(月に半日か1日)だけ勤務すればよいのか?となるが、実際は、週1日、8時半から17時までの終日勤務。(曜日が重ならないように6名は分散勤務だが)。
となると、利用者の自宅を訪問していない時は何をするのかが疑問。 通常は、他の利用者の訪問同行、相談同席や記録作成。しかし、権利擁護事業に係わる様々な雑務?を経験することになるようだ。 完全武装(凄い格好になるようだ)でゴミ屋敷に突入というのもある、と脅された。 得がたい貴重な体験ができるので大いに楽しみ。 (できれば、個人情報保護に反しない範囲で紹介してみたい)
しかし、まずは、電話番で、受話器を取った最初の挨拶が難問。 「はい、西東京市社会福祉協議会、 権利擁護センター あんしん西東京 です」 長過ぎる! 早口言葉じゃない! 言えるかな・・・・。 弱気です。