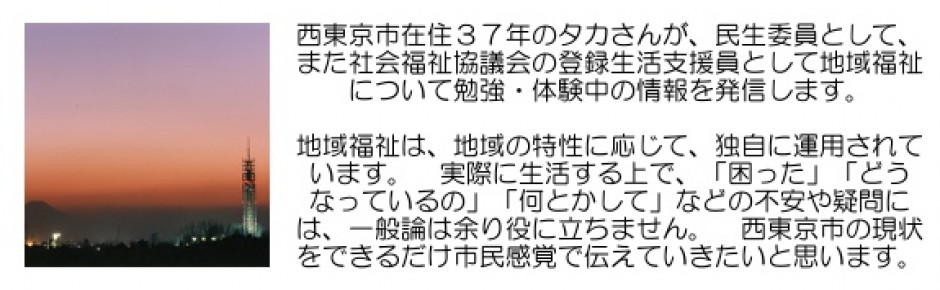7月に民生委員になった際に、障がい福祉部会に所属(会長指示)したが、11月末で一斉改選されるので、本部会も11月末で終了。ということで、今回が最初で最後の出席。
20数名の部会で、男性はたったの一人(他にも1人いたが欠席)。心細い・・・・・・。
議題は二つ。3年間(部会は民生委員の任期に会わせて3年間)の反省と感想、及び来年度の部会への参考意見。皆さんの意見に共通だったのは以下。
障がい福祉を初めて勉強して、個人的には非常に勉強になった。障がい者との接し方やコミュニケーション方法を勉強・実践して、非常に貴重な体験であった。しかし、地域福祉に対して民生委員として、何ができたか・・・。忸怩たる思いがする。年3回の部会開催(他にも色々あるようだが)では組織的な対応は不可能と思う。 続きを読む
2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
最近の投稿
カテゴリー