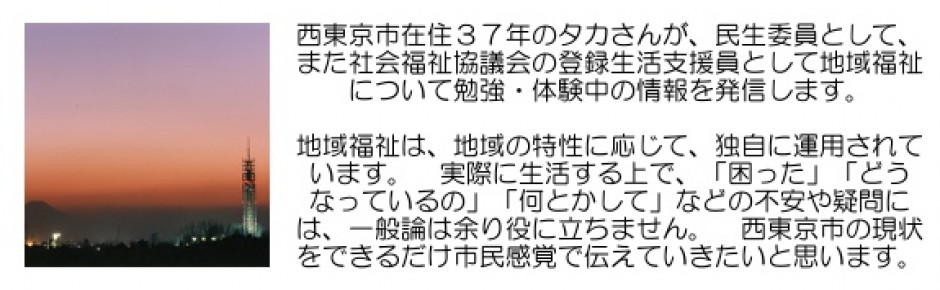講師:安田さん 西東京市福祉部障害福祉課サービス支援係 係長
「無くなる制度の説明をします。しかし、新制定まで5年程度の準備がかかるので、無駄ではありません!」
と、少々混乱するような導入。
実は、今年1月に障害者自立支援法訴訟団と政府が、「障害者自立支援法の廃止と新法の制定」について基本合意したことは知っていたが、その背景や実際の問題点については理解が曖昧だった。今回の説明で、現場の混乱だけはどうにか分かった。
「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします」というのが障害者自立支援法の趣旨。その背景や狙いは、尤もなことが色々書いてあるが、いずれも拙速であったと政府が認めたので、空々しく見える。 が、それなりの理由・理屈があり制定されたものなので、そう簡単に新法と置き換えるのは難しい気がする。
「障害」というと、他人事のように感じるが、現在は、何かしらの持病を持って老後生活を送る人や、また、病気を抱えながら働く人も増 えてきている。これらのハンディキャップを持つ人のサポートは社会全体に移行している。 障害者自立支援法の問題を、単に障害者とその家族だけが考えるのでなく、全ての国民が直視しなければならない問題といえる。
現政権は、障害者自立支援法(H18年4月制定)を廃止。障害者(総合)福祉法(仮称)を制定する。障がい者制度改革制度推進会議により、「そもそも論」から「具体的なサービス」までを議論。近場では、三鷹市長が推進会議に参加。総合福祉部会には、東久留米のピープルファーストの代表が参加。後者の意見書を読んだが、非常に難しい問題が内在しているのが実感できる。当事者にならないと分からない世界かもしれない。
(障害の表記が問題になっている。障礙→障碍→障害→障がい? ハンディキャップ→チャレンジド?など。 ここでは障害と表記)
障害者自立支援法で最も議論を呼んだのが、応能負担から応益負担への変更。全面的に国がサポートしたくても、国の懐事情がそれを許さない。ということで、色々な理屈(詭弁とも言われている)をつけて、応能負担から応益負担としたのだが、裏事情が丸見えなので、説得力に欠ける。障害者とその家族に負担を強いるのは、人権侵害と訴えられ、障害者「自殺」支援法と揶揄されてはいけません。
ない袖は振れないなら、知恵を絞るしかないが、簡単に解決するなら、とうの昔に解決していたに違いない。
社会全体で支えなければならない人、いわゆる社会的な弱者は多い。どのような制度を作っても、必ずあちこちから不満がでる。
また、制度を作ると、必ずその裏をかいて、不正?を働く人もでてくる。(というような話も良く聞くが、国の財政事情が悪くなると、皆さん余裕がなくなりますね。「貧すりゃ鈍す」ですかね。)
間違いなく応益負担から応能負担に戻るでしょうが、バランスのよい制度設計と運用は難しいだろうと、先が思いやられる。
障害者自立支援法自体は、介護保険制度と良く似ている。将来統一する方向であったというのだから当然か。
介護保険と障害者自立支援法の住み分けは、まずは介護保険を適用し、足りない部分は、「横だし・上乗せ」として自立支援法を適用するのが原則。両方の制度 を良く理解し、申請漏れを防ぐことが大切。両者の根本的な違いは、保険制度は財源の半分が保険料ということ(自立支援法は全額公費)だそうだ。 が、介護保険は皆保険なので、税金のようなもの。 応益負担か応能負担かの問題の背景は、似たように感じられるが・・・。
補助金と負担金の違いは重要。補助金は裁量的経費(国が必ずしも保証しなくても良い予算)で、財政状況により圧縮され、予算が不足しても追加交付ができない。 自立支援法の前身の「支援費制度」は、補助金だったので、初年度より補正予算を組む異常事態になったそうだ。 一方、負担金は、必ず支出しなければならない経費で、自立支援給付や生活保護給付などがこれにあたるそうだ。(同じ自立支援法でも、地域生活支援事業は補助金なので、予算消化状況を見ながら事業化を進める必要がある)
西東京市の障害者自立支援法の利用相談窓口は、障害福祉課で田無と保谷に各々窓口がある。サービスは多種多様なので、窓口での相談が必須。相談の結果、利用申請となると、市の職員が106項目のアセスメントを直接行う。この106項目の内79項目は介護保険の要介護認定調査項目と同じ。どうしても身体的な障害が重視されるので、色々問題があるようだ。
(5月10日掲載)