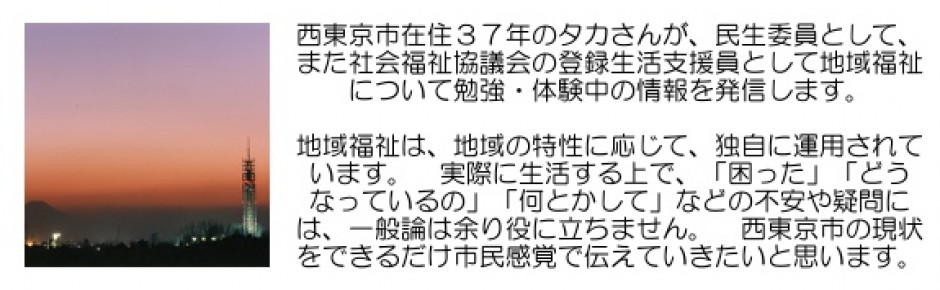地域福祉権利擁護事業、略称は「地権事業」は、
1999年10月、厚生省の予算事業として都道府県社協が実施主体となり、全国300余の市町村社協を中心に、当事者組織や社会福祉法人・NPO団体などと協力の上、痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な者に対し、
・福祉サービスの利用援助
・日常的な金銭管理
・書類の預かりなどのサービスを行うものとして構築された。
この法律は、平成19年に「日常生活自立支援事業」と改称されている。権利擁護事業では、分かり難いという批判があったようだ。
が、各地域では、朝令暮改になるのを恐れ、地権事業をそのまま使っている例も多い。東京都もそうです。
だが、名称は大事です。 まず、そこから話を始めたい(寄り道)。
権利擁護センター? 初めて聞いたときは、思わず首を傾げました。 誰の、どんな権利を擁護するの? 社協が運営するのだから社会福祉に関する権利を擁護するのだ!と言いたいのでしょうが、・・・。 こんな抽象的一般的な言葉では、首を傾げるのは当然。 日常生活自立支援の方が、具体的です。
あんしん西東京? これも、抽象的だなぁ。 安心の概念は広いです! 最初に聞いたときは、交通安全の標語かと思いました。 ピーポくんのステッカーなら我家も貼っています。
再び権利擁護? 社会福祉の権利擁護というのもとっつきにくい。 昔のように人権擁護と言った方が馴染みがあるが・・。 人権擁護は、人権を守るというニュアンスであったが、権利擁護は、権利を主張するという意味合いが強いようだ。 権利擁護という名称には、ある想いが込められているようだが、分かり難いものは分かり難い。
分かり難さから言えば、生活支援員も同様。社会福祉の領域では、ヘルパーさんという職種があるが、このヘルパーを和訳すれば生活支援員になるのではないか? 掃除や料理をしたり、買い物に行ってくれる、そんなイメージが浮かぶのは、私だけか?
成人後見人なら特殊用語だし、未成年後見人から何となく機能が類推できる。が、生活支援員では、ヘルパーと勘違いする人を咎めることはできない。
付け加えると、我々は登録生活支援員である。登録って何?である。 西東京市社協の特殊用語とのこと。 今までの生活支援員は、常勤の社員であったが、我々は必用な時だけ働く臨時職員として登録されているのが理由らしい。 なんとも紛らわしい。
権利擁護センターあんしん西東京のバックボーンである権利養母制度はなぜ、登場したのか、その目的や背景は?
平成12年、介護保険の登場に合わせて、大きな変化があった。
・措置制度から選択利用制度へ
・利用者保護制度の創設へ
この方向性は、これまでの措置制度が利用者の選択の権利や自己決定を認めていなかったという反省から、多様な福祉サービス供給事業者からサービスを選び、契約によりサービスを利用するというものである。 と言われている(色々解説もあるが)
しかし、契約となると、事業者と対等な能力が保持されているとは言い難い福祉サービス利用者(例えば、痴呆高齢者など)には、何らかの支援が必用である。具体的には、民法改正による成年後見人制度と社会福祉法による地域福祉権利擁護事業である。
さらに、権利を擁護し補完・補充するものとして、情報公開や第三者評価そして苦情解決などが社会福祉制度の中に取り入れられている。これらの支援制度の相互の関連性を考え(実際、成年後見制度と地権事業との境界は曖昧で重なり合っている)、利用者にとって最適な助言と「福祉サービスの利用援助」サービス等を提供するのが権利擁護センター「あんしん西東京」のミッションです。
タカさんのように、東京都主催の成年後見人等候補者養成基礎講座の修了者や予定者が、登録生活支援員として採用され実習を積むのは以上のような理由があるからです。
西東京市の権利擁護センターあんしん西東京の相談利用件数は、高齢化の進行に伴い増加している。
問合せや相談件数は日に10件。それを4名の相談員で対応。
生活支援の契約数は40件。6名の常勤の生活支援員が対応。処理能力の限界だそうだ。
できるだけ早く、登録生活支援員として1人立ちし、増大するニーズに応えていきたい。
(5月6日掲載)